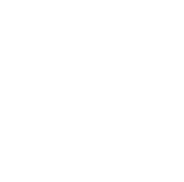AIのEQはどこまで進化しているのか?─ChatGPTのEQスコアとGPT-4.5の新たな可能性
私たちの会社では、Six Seconds社が提供するEQフレームワークを活用し、職場での感情知能(EQ)を高める取り組みを行っています。このフレームワークを通じて、自己認識を深めたり、同僚のブレインスタイルを理解し、より効果的なコミュニケーションを図ったりしています。
日常的にAIを活用している中で、その反応の優しさや安定したメンタルに驚かされることはありませんか?まるで感情を持っているかのような応答に、「AIのEQってどれくらい高いのだろう?」と興味を持ち、調べてみました。
ChatGPTのEQスコアは?
Six Seconds社は、ChatGPTにEQアセスメント(SEI®)を実施し、その結果を公表しています。その結果、ChatGPTのIQスコアは人間の99%を上回る一方、EQスコアは人間の32%を上回るにとどまり、平均以下という結果でした。
https://www.6seconds.org/2025/02/24/ai-fakes-it-good-leaders-keep-it-real/
この結果は、AIが感情を実際に体験するのではなく、あくまでシミュレーションしているに過ぎないことを示しています。また、企業のマネジャー層には、「感情については理解しているが、それらは複雑で面倒なので避け、論理の快適さを好む」という傾向が見られ、これはまさにAIのアプローチと似ています。
しかし、分析的なタスクではAIが人間を凌駕することが明らかになっている今、リーダーとして生き残るためには、EQの活用が鍵となります。
GPT-4.5の登場とEQの進化
そんな中、2025年2月27日にOpenAIからGPT-4.5のリリースが発表されました。
https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-4-5/
このモデルは、より広範な知識ベース、ユーザーの意図を汲み取る能力の向上、そして進化した「EQ(心の知能指数)」により、文章作成、プログラミングの向上、実用的な問題解決など、多様なタスクに役立つことが期待されています。
GPT-4.5は、より自然な会話、感情知能の向上、そしてAIの誤情報生成(いわゆる「幻覚」)の減少を特徴としています。OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏は、このモデルを「思慮深い人と話しているように感じられる初めてのモデル」と評しています。
EQはどのように育まれるのか?
EQは、自己認識、自己管理、社会的認識、関係性の構築、責任ある意思決定といったスキルを含み、子どもから大人までの成長過程で育まれます。特に、社会的・情動的学習(SEL)という教育アプローチが注目されており、感情の認識や調整、共感力、良好な人間関係の構築などを学ぶことができます。
大人になってからも、EQは意識的なトレーニングや実践を通じて向上させることが可能です。例えば、マインドフルネス瞑想、自分の感情を感じ取る練習、他者の視点を想像するなどの方法があります。
AIとの共感的な対話がもたらす未来
数年前、シミュレーションゲームの「酒場」で、酒場のマスターが生成AIの能力を活用し、自然言語で、パターンの組み合わせとは思えない豊かさで、話を否定することもなく、優しく話を聞いてくれる世界観を見たとき、人間同士のコミュニケーション空間に居づらくなる人が増えるだろうと直感的に感じました。
AIのEQが一層高まり、適度な距離を保ちつつもより共感的な対話が可能になると、私たちの社会はどのように変化していくのでしょうか。
AIの優しさの背景にあるビジネスモデル
AIも競合プレイヤーが多い月額課金モデルであることから、ユーザーに対して必要以上な指摘はせず、ある意味迎合して契約を継続してもらえるように設計されている側面もあるのではないでしょうか。これは、会社の先輩が新人に対して「やさしい」向き合い方をするのと似たロジックかもしれません。
「耳が痛いことも言ってほしい」とデフォルトのプロンプト設定をしておけば、パーソナルユースでは調整が可能かもしれません。
まとめ
AIのEQ(感情知能)が進化を遂げている一方で、AIとの対話には「エコーチェンバー現象」のような側面が強いと感じることがある方もいるかと思います。最新のAIモデルでは、過去のチャット内容を参照し、前述のように、よりパーソナライズされた「受け入れやすい」回答を提供する設計がなされています。
また、対話型AIは倫理的かつ模範的な回答を前提としているため、予測可能な応答に留まりがちです。しかし、私たち人間の「感情」とは「予測可能な感情の応酬」で育まれるといえるでしょうか?
自分には全く予想もつかないような感情の表出や、言語で表現することに限界を感じて表現されたもの(芸術作品など)から得られた戸惑いや感動によって、感情の襞が育まれているという側面を私たちは見逃すことができません。
人間の可能性というのは、自分個人では全く予測不可能であった境地へ触れる「余地」を愉しむところにあると考えられるのではないでしょうか。
AIのEQは着実に進化を遂げていますが、AIは感情を実際に体験することはできません。私たち人間は、感情を感じ、共感し、他者と深い関係を築く能力を持っています。
AIとの共存を考える上で、私たち自身のEQを高めることが、より良い未来への鍵となるでしょう。本来、AIは関係ない大切なコトですが、EQが一見高いAIの存在が私たちに「人間らしさとは何か」や、EQの重要性を再認識させ、感情や共感の重要性を再評価する機会を提供しています。
目の前の人や出来事に真摯に向き合い、コミュニケーションを回避せず、感じ、考え、行動すること。この基本的な姿勢こそが、AI時代においても変わらぬ人間の強みであり、社会の持続的な発展に寄与するものと考えます。
最後に、目の前の美しさに心を動かす力をこそ人間の「よいところ」と表した一節を添えておきます。
ぽかんと花を眺めながら、人間も、本当によいところがある、と思った。花の美しさを見つけたのは、人間だし、花を愛するのも人間だもの。
— 太宰治『女生徒』