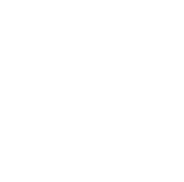プロフェッショナルを阻む“善意の落とし穴”
「善意だから」という出発点は温かく、チームを思いやる美しい言葉です。
しかし、その善意に頼った“アマチュア的な行動”は、意図せぬ混乱や事故につながることがあります。
本稿では、“善意ベースの仮定(assumption)”による問題に焦点を当て、実例とGoogleの文化変化の背景も織り交ぜながら、注意点を探ります。
1. 善意の仮定が招く「確認なき行動」のリスク
「これは問題ない」「こうした方がよい」と思い込み、関係者への確認を経ずに手を動かす——これが善意ベースのアマチュアの典型です。
意図は純粋でも、
- 意思決定ルートを無視し、
- 全体のバランスや影響範囲を無視し、
- 後工程や他部署への確認を怠り、
結果的にコミュニケーションエラーやシステム障害など、大きな混乱を招きます。
確認を飛ばした一手が、プロジェクト全体の信頼性を揺るがすこともあるのです。
2. 実例:サイトの見た目を改善しようとした"善意"が事故に
「見た目をもっとおしゃれに」と意気込んだ開発者が、ソースコード(CSSやテンプレート)に勝手に手を入れた結果、想定外の影響が発生し、チェックアウト画面が壊れて大規模な売上停止に・・・。
この“良かれと思って”の修正が、社内にも顧客にも深刻な影響を与えてしまうケースは決して珍しくありません。
*なお、ECシステム「Shopify」の世界ではチェックアウトの制御可能領域は意図的に一定の制限があり、このような影響を回避できる構造となっています。
ITの世界では本来、変更を行う際に影響調査(impact analysis)やリグレッションテストなどの手法を用いて影響範囲を把握し、問題が生じないことを確認します。しかし、
- フリーランス的に一人開発しか経験していない、
- 逆に巨大組織の中でごく一部のパーツしか担当してこなかった、
といった環境では、こうした「変更管理」の概念そのものが必要とされず、身につかないケースがあります。その場合、全体を見渡して一貫性ある仕事をする上で欠落している視点があるため、プロの現場ではアマチュア的と評価されかねません。
3. 「許可なく動く文化」は時にアップサイドよりもリスクが大きい
シリコンバレーでは「Don’t ask for permission(許可を求めず動け)」というカルチャーが語られることがありますが、その実、すべてがうまく回るわけではありません。むしろ、大きくなった組織ではこうした文化の「コスト」の方が目立つこともあります。
例えば、GoogleのTGIF(創業期の定例タウンホール)は元来、自由な質問と開発文化の象徴でした。しかし、スケールするにつれて漏えいや非公開への懸念が高まり、CEOサンダー・ピチャイはこの文化を縮小させ、開催頻度の削減や内容の厳格な限定を決定しました。(ref)
これは、「自由に動けること」自体を否定するのではなく、確認と構造を欠いた自由がいかにリスクを内包するかを示す転換点です。
4. バランスあるチャレンジ文化を設計するには
もちろん、チャレンジ精神やハッカースピリットそのものを否定するわけではありません。むしろ挑戦こそが成長の源です。ただしここで一つ問いを立てたいと思います。
「改善案をプロセスを経ずに即実装したいという欲は、本当に“改善”なのか? それとも単に“やりたいことをやっているだけ”ではないのか?」
この問いは、組織の中で個人の行動を位置づけ直す視点を与えます。
- プロセスを経ることでチーム全体に貢献するのか、
- それとも自己満足で終わるのか。
その分水嶺を見誤らないことが、プロフェッショナルに求められる態度です。一方で、チャレンジのコストを過剰に積み上げると、メンバーの挑戦意欲そのものが削がれてしまうリスクもあります。「これ、やったら良さそうだけど、説得とか、影響の評価とか面倒だから、まあこのままでいっか・・」といった消極的な姿勢を生んでしまう恐れがあります。
そのため、マネジャーには、必要なガードレールを敷きながら、挑戦心を抑えすぎないバランス感覚が求められます。
まとめ
善意は美しいスタートラインです。
しかし、確認なき仮定やプロセス軽視は、組織に混乱をもたらします。
確認とコミュニケーションを伴ったチャレンジこそが、個人にも組織にも持続的な価値を与えてくれるのです。