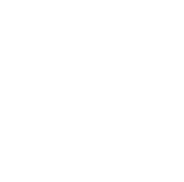ECサイトの「内製化」を阻む、人事制度という見えない壁
はじめに:本稿で伝えたいこと
フラッグシップCEOの神馬です。
近年、企業の間で「ECサイトの開発を内製化したい」というニーズが急速に高まっています。しかし、内製化は単に社内にエンジニアを雇えば成功するものではありません。
本稿では、内製化の推進を阻む「人事制度という見えない壁」に注目し、制度設計とカルチャー設計を含めた構造的なアプローチこそが内製化成功の鍵であるというメッセージをお伝えします。
IT企業でない企業がエンジニア組織を持つということ
学生時代、アメリカのコーヒーショップで何気なくその会社の求人ページを開いたときのことを今でも覚えています。そこには、バリスタや店頭スタッフに混じって、「Frontend Engineer」「Data Scientist」などの募集が並んでいました。
当時の私は驚きました。コーヒーショップなのに、エンジニア?そんな職種はIT企業のものだと思っていた常識が、その瞬間に覆されたのです。
それから15年、AppleやAmazon、Teslaのように「一見すると製造・販売会社に見えるが、本質はIT企業」という会社が社会を席巻してきました。
つまり「どんな顔をしていても、実体はIT企業」であることが、世界の勝ち筋となってきたのです。
内製化の波と、その見えない壁
私たちも日々、日本の大企業と共にECサイトの開発や運用に関わっていますが、近年「開発の内製化」への関心が高まっていることを強く感じます。
経営戦略・ブランド理念を正しく理解し、それをスピーディーに体現できるエンジニアリングチームを、社内に持ちたい。そんな機運は確かに存在しています。
実際に、VP of Engineering等の責任者を採用できた企業では、チーム構築がうまく回るケースも出てきました。
しかし、全体として見ると、立ちはだかるのは「人事制度の壁」です。
終身雇用型人事制度と、エンジニア文化の断絶
特に製造業などの大企業では、前提となっている人事制度がエンジニア採用と致命的に噛み合わないことが多々あります。
- 終身雇用を前提とした昇進・昇級ルール
- 職能よりも年次・社内試験を重視する評価制度
- 異動や出向が前提の人材マネジメント
こうした制度は、ITエンジニアが求める「技術の深化」や「専門性の評価」とは対極にあります。
人事制度が変わらないままでは、優秀なエンジニアを採用できても、定着・活躍させることができない。実際、「良い人をたまたま採れたが、制度にフィットせず短期で辞めてしまった」という話を何度も見てきました。
たとえば、エンジニア向けに以下のような制度設計が考えられます:
- 技術スキルに応じた専門職等級制度
- 異動を前提としないスペシャリストキャリアパス
- 年次評価よりも成果と成長に基づいた柔軟な昇進制度
評価軸のズレがマネジャーを苦しめる
さらに問題なのは、評価軸の不一致です。
会社は「全体調整やマネジメント能力」を評価したいが、エンジニア本人は「アーキテクチャ設計力や技術スキル」を高めたい。
このギャップにより、上司となるマネジャーが板挟みになってしまう例も少なくありません。
理念は共有、制度は別。カルチャーの分化が鍵に
このような背景から、近年注目されているのが別法人(子会社)としての開発組織運営です。
大きな理念やビジョンは親会社と共有しつつも、人事制度や働き方はエンジニア向けに最適化する。
ベンチャー的なスピード感と自由度を持ちつつ、ブランドとしての一貫性も保てるため、現実的な選択肢になりつつあります。
外部に残すリスクヘッジという視点も
私たちが長年お客様のEC運用に関与する中で実感しているのは、「歴史と仕様を知っている人」が外部にいることの価値です。
社内人事は数年ごとの異動が当たり前。プロジェクト担当が変わるたびに仕様の引き継ぎが発生し、開発効率が落ちてしまいます。
その点、長期で関わる外部パートナーは「社外にある知的資産」として機能できる可能性があります。
内製化の器をどう作るか
内製化は決して万能ではありません。
重要なのは、「制度設計とカルチャー設計を含めて、内製化の器をどう作るか」という視点です。
表面的な内製化ではなく、制度・評価・カルチャーを含めた構造的な内製化戦略こそが、EC運営の競争力を左右していくはずです。
まとめ
本質的な内製化とは「制度と文化を含めて自社の開発チームをどのように位置づけるか」の設計であり、その成否は“人材の定着と活躍”に直結します。
経営・人事・開発が三位一体となってこの壁を乗り越えることこそが、これからの企業に求められる本質的な変革です。