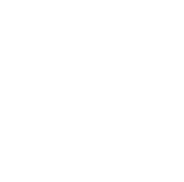ITエンジニアの特別扱い。その甘さは、本当に甘いのか?
はじめに
フラッグシップCEOの神馬です。
このコラムは、私自身がかつて企業の「唯一のIT担当・Web担当」として働いた経験や、エンジニアであると言う前提でコミュニケーションをされる経験から生まれた内省です。当時、「エンジニアだから」という理由だけで、一般的なビジネス職に求められる対人スキルや業務理解のレベルが免除されていることに気づきました。事業が必要とする機能性を提供している限り、私のコミュニケーション上の問題点(あいつ当たり前の挨拶ができないけど、まあいいか、的な)や業務理解の浅さが大目に見られ、知らず知らずのうちに「特別扱い」という甘い環境に身を置いていました。
その環境の甘さは、本当に甘いのか?と言うのがこのコラムのポイントです。
エンジニア優遇の時代が抱える見えない代償
ITエンジニアは、今や世界中で引く手あまたの職業である。エンジニアの需要は年々高まり、供給は不足し、高給・特別待遇が当たり前の世界が続いてきた。企業としても、レバレッジの効くシステム開発業務を重視し、「コードを書けるエンジニア」の価値を高く評価してきた。
高く評価するどころか、多面的に、この人たちがスムーズに仕事をできるような仕掛けが散りばめられ、「臭いものには蓋をして」やりたい放題な環境の整備が進んできた。
しかし、この状況は本当にエンジニアにとって理想的なものなのだろうか。
このコラムで述べることは全て、そう言う傾向があると言う話で、断定するものではないが、私は、エンジニアがエンジニアリングだけに向き合うよう仕向けられた結果、大人として成長する機会を奪われてきたと考えている。
エンジニアが「甘やかされる」構造
技術が評価され、企業からもチームからも「彼/彼女がいないと困る」と思われる。これは一見すると理想的な状況に見える。しかし、これはエンジニアを「職人」として特別扱いすることで、人間としての成長を妨げる構造を生み出している。
映画『ソーシャル・ネットワーク』で描かれたように、プログラマーが“Zone(ゾーン)”に入るときは外界からの干渉を極端に嫌い、その集中を壊すことがタブーとされる。実際、心理学でいうようなな「フロー状態」を中断されると、元に戻るのに20分以上かかるとされ、プログラマーの世界では、特に優秀なプログラマーに対して、「コンテキストスイッチのコストを負わせてはいけない」という風潮が一般化している。
この「ゾーンを守る文化」自体は生産性や品質を高める合理的な背景を持っている一方で、この発想が過剰に適用されがちなことから、皮肉なことにエンジニアの“甘やかし”につながる温床にもなっている。すなわち、プログラムを書いてソフトウェア開発の生産性を最大化するという機能性が最優先されるあまり、コミュニケーションや対人関係の未熟さは見過ごされ、人間的な成長機会が先送りにされてしまうのだ。
専門性に頼るキャリアの限界
エンジニアが専門職としての道を突き進むことは、決して悪いことではない。しかし、その道がいつまでも続くとは限らない。
言うまでもないが、コードを書くAIの台頭により、「プログラムを書けること」自体の価値が揺らぎ始めている。また、単純に加齢による問題もある。40代・50代になったとき、昔ほどの体力はない。経験や技術力があっても、求められるものとして、「人間としての当たり前の力」の比重は必然的に大きくなってくる。
- 組織の中で、円滑に意思疎通を図れるか
- ビジネスの課題を理解し、エンジニアリング以外の問題にも向き合えるか
- 難しいコミュニケーションを避けずに、他者と対話できるか
年齢を重ねていくうちに、こうした能力の不足に直面し、「今さらどうしようもない」と感じることになるかもしれない。技術だけを頼りに生きてきた結果、人間としての成長が止まったままでは、キャリア・人生の選択肢が限られてしまう。
エンジニアを「一人前の大人」として扱う文化を作る
当社では、エンジニアを特別扱いしない。技術力があるからといって、人間的な成長を後回しにすることは許さない。
- 対峙すべき人間性・コミュニケーションの課題にはしっかり向き合う
- ダメなものはダメとはっきり伝える
- つまるところ、「一人前の大人」として扱う
エンジニアが職人としての人生に甘んじることなく、人としても成長できる環境を作ること。それが、私たちの目指す組織のあり方だ。
また、あなたがエンジニアであれば、エンジニアが一人または少数しかいない組織で、出来ることの幅を広げ、大活躍するのもそれはそれで良い経験だが、相当人間の出来た+ITも分かる経営でない場合、常にこの罠と隣り合わせな構造にあると言わざるを得ない。
エンジニアがたくさんいる組織で、尊敬できるエンジニアの先輩がいれば、同じ土俵にいる分、対応も必然的に、妥当な厳しさを期待できるでしょう。
これからのエンジニアは、技術だけでなく、人としての強さを持つべき時代に突入している。成長の機会を逃さないように、今、何が必要なのかを問い直すことが求められている。