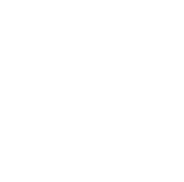インクルーシブ・ネーミングとは。Githubのデフォルトブランチ名変更を受けて

フラッグシップCEOの神馬です。
近年、IT業務やソフトウェア開発の現場では、より包括的で差別のない表現を使用する「インクルーシブ・ネーミング(Inclusive Naming)」への関心が高まっています。
開発者にとっては馴染み深いと思いますが、2020年10月より、この動きの一環・象徴的な出来事として、GitHubはリポジトリ作成時のデフォルトブランチ名を従来の「master」から「main」へ変更しました。
4年以上も放置していた"もやもや"に着手したのがこの記事ということになりますので、時代を捉えていない大きいディレイについてまず謝罪します...
GitHubのデフォルトブランチ名変更の背景
「master」という用語は、歴史的に「master/slave(主人/奴隷)」という主従関係を示す用語として使用されてきました。この表現が人種差別的な背景を連想させるとして、ソフトウェア業界全体で見直しが進められています。
Black Lives Matter運動は2013年から始まっていましたが、2020年のミネソタ州でのジョージ・フロイドさんの事件を機に加熱し、なんとソフトウェア業界にも大きい変化をもたらしたのです。
2020年6月、ソフトウェアの自由とオープンソースの促進を目的とする非営利団体であるSoftware Freedom Conservancyは、Gitプロジェクトと共に、デフォルトブランチ名「master」が一部のユーザーにとって不快であることを認識し、これを変更する意向を表明しました。この声明では、Gitが新しいリポジトリを作成する際の最初のブランチ名をユーザーが指定できる機能を追加すること、また、コミュニティプロセスを通じてデフォルトブランチ名を「master」から別の名称に変更することが検討されていると述べられています。
同年10月にはGithubはポリシーを変え、システム変更もリリースしています。
インクルーシブ・ネーミングとは
上記に例に限らず、IT業界でも、差別や偏見を排除し、より包括的な言語を使用する「インクルーシブ・ネーミング(Inclusive Naming)」への取り組みが進んでいます。この動きの一環として、2020年にIBMやRed Hat、VMware、Cisco、Linux Foundationなどの主要IT企業が協力し、「Inclusive Naming Initiative(INI)」を結成しました。
INIの目的は、ソフトウェアやドキュメント内で使用されている差別的または排他的な用語を特定し、中立的で包括的な表現に置き換えることです。例えば、「master/slave」という用語は、「primary/secondary」や「leader/follower」といった中立的な用語への置き換えが推奨されています。
日本のビジネス環境においては、英語圏ほど文化的背景を踏襲していないことから、問題意識は深くないのものの、外資系企業やその取引先などからこうした用語の見直しが求められています。
そんな中、自分の中でも疑問だったのが、商品マスターという言葉です。IBM出身の同僚が軽く問題提起したことがあり、「確かに」と思っていたものの、深く理解していなかったことから調査し、この記事を書くに至った背景です。
日本における「商品マスター」という用語について
日本のビジネス環境では、「商品マスター」という用語が一般的に使用されています。この場合の「マスター」は、データの基準や正確な情報源を指すものであり、差別的な意味合いは含まれていません。
しかし、その正しい定義に関わらず、「マスター」という言葉自体に違和感を覚える方もいるかもしれません。そのような場合、以下のような代替表現を検討することが考えられます:
- 商品カタログ:商品の一覧やカタログを示す。
- 商品DB:商品情報を一元的に管理するデータベースを指す。
文脈と受け手に応じた調整の視点
「master」という言葉が問題視される背景には、従属関係(master/slave)を前提とした技術的な文脈で使われてきたという歴史的背景があります。
ただし、あらゆる「マスター」という表現が常に不適切というわけではなく、文脈によっては「基準」や「熟練者」「支援者」といった肯定的な意味で使われることも多くあります。
重要なのは、相手やコンテキストに応じてその言葉がどう受け取られるかに配慮できること。仮に相手がその言葉に対して違和感を抱いているのであれば、それに合わせて表現を調整する柔軟性を持つ、というのが私たちのスタンスです。
「スクラムマスター」という名称について
ちなみに、当社の組織図にも「スクラムマスター」という役職名があります。
この場合の「マスター」は、いわゆる従属関係を示す「master/slave」の文脈とは異なり、チームを支援し、円滑な開発を導くファシリテーター的存在を指しています。アジャイル開発における公式な用語でもあり、業界内でも広く使用されており、現時点では明確な代替語も存在しません。
そのため、当社においてもこの役職名は引き続き使用していますが、今後も文脈や変化に応じて適切な対応ができるよう意識していきたいと考えています。
言葉の選択は、文化と価値観を映す
ちょっとしたことですが、どういう言葉を使うか、使わないかは、価値観を反映するものであり、その人・組織の文化にもなります。
当事者に何も原因がない理由で、誰かが傷つくかもしれないワードである可能性があれば、別の言い方を検討できることで、ちょっぴり、より尊重し合える社会の実現に寄与することが出来るというと言い過ぎでしょうか。
とはいえ、いき過ぎたポリコレへの違和感もあります。
そんな中でも、少なくともこれらのことを知識として文脈含め認識し、文脈に応じて適切に選択できるようにしておくことが大事だと思い、私見ながら発信させていただきました。