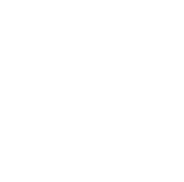Flagship初の”アーキテクト”になってみて
フラッグシップで働くメンバーのリアルな声をお届けします。今回は、アーキテクトチームのReonaにインタビューしました。
── まずは自己紹介をお願いします。
Reona「Flagshipには当初、フロントエンドエンジニアとして入社しました。
当時はプロジェクトのリソースの関係で、日本語が話せて技術が少しわかる人材が必要ということで、Shopify Plus ECサイトの新規立ち上げ案件に配属されたのが最初です。
その後、サイトをリリースして、昨年の9月頃にアーキテクトというチームが立ち上がって、そこに移る形になりました」

──Flagshipにジョインされる前は、どんなことをされていたんですか?
Reona「あるファッションブランドで、STORESという日本のECストア構築サービスを使ったストアの運営者として働いてました。
STORESはノーコードでECサイトが作れるんですが、受注販売をしていたので、標準機能だけでは足りなくて。
GoogleスプレッドシートやGAS(Google Apps Script: Googleが提供するJavaScriptベースの開発プラットフォーム。スプレッドシートなどのGoogleサービスを自動化できる)を使って、自社用の受注販売システムをいろいろ作っていました。
そのときも、
『いつかはIT企業で働いてみたい』という思いがずっとあったのですが、プロとしてコードを書いてお金をもらったことはなかったので、自分がどこまで通用するのかも全然分からなくて。でも、自社で使う業務効率化ツールをいくつも作っているうちに、『もっとチャレンジしてみたい』と思うようになってきました。
EC業界にすごく強いこだわりがあったわけじゃないんですが、自分の経験が活かせると思えたのがFlagshipでしたね」
パソコンに「使われる側」ではなく「使いこなす側」になりたかった
──IT業界にチャレンジしたいと思ったきっかけは?
Reona「プログラミングを始めたのは大学時代なんですけど、それまでは"パソコンにちょっと詳しい人"っていう感じでした。元々モノづくりも好きだったので、その延長線上でプログラミングがすごく楽しかったんです。パソコンって道具としてとても優秀だし、使われる側じゃなくて、使いこなす側でいたいなと。
大学ではIT系の専攻ではなく、建築を学んでいたのですが、課題の中に「ITを活用した図書館の設計」があって、それをきっかけにITについて歴史も含めて深く調べることがあって。ダグラス・エンゲルバートやアラン・ケイとか、iPadの元になったような発想をしていた人たちのことを知って、こういう未来を予見できる人が社会を作ってるんだと衝撃を受けたんです。
ただ当時は、”情報系の学部を出てないと無理なのでは”という思い込みがあり、IT業界には進まなかったんです。でもFlagshipの方が、”大変だけどキャッチアップできると思う”と言ってくださって、そのチャンスは逃せないなと思いました」

アーキテクトは”エンジニアの翻訳者”
──現在はアーキテクトとして、どんな仕事に取り組んでいるんですか?
Reona: 「主にECサイトのリニューアル案件を担当しています。新しいストアをShopifyで作って、旧サイトからの機能の移植やデータ移行、要件定義、設計などを行っております。
アーキテクトという職種を一言で説明すると、技術的な理解を持って、PMやクライアントに説明できる人です。契約や交渉ごとはPM(プロジェクトマネージャー)が担いますが、実現可能性や方法については、アーキテクトが技術の視点から整理して伝えます。
アーキテクトとPMの違いとしては、PMは契約やクライアントとの調整、日程管理などフロントに立つ役割が中心で、アーキテクトは『できる・できない』『どれくらい時間がかかるか』など技術的観点から説明する立場です。開発者が話していることを理解して、PMやクライアントに翻訳して伝えるのがアーキテクトの役割だと思っています。
──アーキテクトは、エンジニアの代弁者みたいな役割でもあるんですね。
Reona「そうですね。でも、単に開発タスクを最適にこなすだけじゃなくて、そもそもその運用が必要なのかとか、もっと上流の視点で判断する必要もあります。倉庫連携や会計周りなど、ECに関わる全体のシステム構成を理解したうえで、最適なソリューションを導き出す専門職だと思います」
プログラミング言語に精通するよりも大切なこととは?
──聞けば聞くほどやりがいがありそうですが、同時に大変そうな立場にも見えます。
Reona「まさに最近、役割の線引きを強く意識しています。以前はPM的な業務もやっていた時期がありましたが、それはやっぱり専門性が違うと感じました。
アーキテクトは技術と運用の橋渡しに集中した方が、プロジェクトがうまく回る。やるべきことややれることが広く見える立場であるからこそ、このポジションの役割をしっかり整理していくべきだと思っています。
Flagshipには助けてくれる人たちがたくさんいます。なので今はなんとかなっていますが、今後アーキテクトが増えたときは会社として体制面の整備も必要になると思います」
── 今後アーキテクト職を目指す人がいるとしたら、どんなマインドやスキルが必要だと思いますか?
Reona「まず、Shopifyの仕様はもちろん、物流や基幹システム、税金などの業務知識をキャッチアップしていける探究心が必要です。開発ドキュメントを読む力も大事ですね。
ただ、プログラミング言語にすごく精通している必要はないと思っていて、それよりも「良いアーキテクチャとは何か」を判断するセンスとか、特にShopifyはSaaSなので、フルスクラッチのシステムとは違い制約に直面する機会も多々あるので、制約の中で最適解を見つける力が重要だと思います。
自分は生成AIもフル活用してますし、他のプロジェクトの仕様書やドキュメントを見たり、社内の例を参考にしたりしています。あと、週一の勉強会もあって、アーキテクトやエンジニア、PMが一緒に議論しています。そこから得られる視点はとても貴重です」
英語はみんなネイティブじゃないから大丈夫
── Flagshipはフルリモートですが、Reonaさんはオフィスにも来られてますよね?
Reona「はい、週に2回くらいです。やっぱり直接話すことで得られる安心感や共感ってあるので、時間を見つけてオフィスに行っています。リモートだと孤独になることもあるので、同じ状況の人たちと実際に話せることは、自分にとって大事なんです。
もちろんフルリモートの良さもあって、通勤がないのは大きいですね。家のこともできるし、時間の使い方に柔軟性があります。
ただ、裏返すとちゃんとコミュニケーションを取らないとすぐに孤立するということでもあるので、そこは意識しています。最近は社内コミュニケーション改善の委員会も立ち上げて、ドキュメント整備やSlackの使い方の改善などに取り組んでいます。」

── Flagshipのカルチャーはどのようなものですか?
Reona「まず、多国籍なメンバーで構成されているので、考え方の違いが面白いです。英語が公用語ですが、非ネイティブが多くて、『俺も勉強して喋れるようになったんだ。みんなネイティブじゃないから大丈夫だよ』って言ってくれた人がいて、それがすごく印象に残っています。自分も経験したことだから、伝えられなくて困っている気持ちを察してくれる人が多いんですよね。
もちろん言語の違いについて、最初はギャップがありました。でも英語ができないから黙っていたら、プロジェクトは進まない。だからこそ勇気を出して話して、仕事を通したチームメイトとして、同僚と仲良くなれることも多かったです。
プロジェクトが大変なときは、国を超えて助け合えるのも魅力ですね。ベトナム語で”Cảm ơn(ありがとう)”って言ってみたら、ベトナム人のメンバーがめちゃくちゃ喜んでくれて、次の日の会議でそのメンバーが日本語で”ありがとう”って言ってくれた。そういう瞬間がすごく嬉しいです。
言葉の壁よりも、前提の共有や情報の質がコミュニケーションの本質だと思います。長すぎても読まれないし、短すぎると伝わらない。英語が上手かどうかというより、相手に何を伝えるべきかを意識することが大事ですね」
”地図を描く側”になるか、“描かれた地図を見る側”でいるか
──Flagshipの掲げているバリューには「Start with Hacker Spirit」「Be Professional」「Pay it Forward」があります。Reonaさんがもっとも共感しているものはなんですか?
Reona「全部大事ですが、Be Professionalは特に意識してます。人数が少ない会社で、大手企業を相手にするとなると、一人ひとりの質がすごく問われるんですよね。やるべきことの幅も広くて、でもクオリティは落とせない。だからプロフェッショナルとしての自覚が求められる場面が多いと思います。」
Hacker Spiritを感じる出来事としては、最初のプロジェクトで、エンジニアリングマネージャーに『これってできますか?』って聞いたとき、『世の中にできないことはないよ』って言われたことですね。できない前提じゃなくて、どうやってやるかを考えるっていう姿勢に衝撃を受けて。それ以来、私も自然とそういう考え方になりました」
──Flagshipのパーパス「まだない地図をつくる」については、どんな風に捉えていますか?
Reona「この会社は、まだ歴史が長いわけじゃないし、常にアップデートされています。だからこそ、絶対的な正解があるわけじゃなくて、最善策を自分たちで考えてつくっていく、という姿勢がすごく大事だと思っています。自分が”地図を描く側”になるのか、“描かれた地図を見る側”でいるのか、その意識の差って大きいと思います。」
入社半年でトロントのイベントに参加してみて
──今後もアーキテクトとしてやっていくつもりですか?それとも、別の可能性も考えてますか?
Reona「アーキテクトというポジションは、正直、自分が名乗って始めたというより、あとから名前がついたという感覚なんです。もともとは独学で開発していた側なので。
今はPM定例にも、開発側の定例にも参加していますが、どちらかというと開発側の視点が好きなんです。技術がどう役に立つかまでを一緒に考えるような立ち位置で、そこを深めていきたいなと。
以前上司から聞いた「技術とビジネス、どちらも本当に理解している人って少ない」という言葉が印象的で、テクノロジーをどうやってサービスに転換するかを、一瞬でイメージしてしまう力に圧倒されます。そういう姿に憧れますね。」


──その姿が、将来なりたい「アーキテクト像」なんですね。
Reona: 「そうですね。最近はクライアントとの調整も増えていましたが、もう一度技術に深く入り直したい気持ちも強いです。
昨年、入社して半年くらいのタイミングだったんですけど、トロントで行われたShopifyのエディションイベントに、幸運にも参加させてもらいました。
前日はShopify全体のグローバルイベントが開催されていて、世界中から関係者が集まるんです。4000人くらい参加していて、ブースごとにCheckoutやStorefrontなどの技術セッションが行われていて、まさに開発力で世界をリードしようというShopifyの姿勢を体感できたイベントでした。
去年Flagshipから参加したのは2名なのですが、私は当時まだ駆け出しで、エンジニアとしてもバリバリというわけではなかったんですけど、選んでもらえました。嬉しかったですね。選ばれた理由は聞きませんでしたが(笑)」(今年は4名が参加しました)
自分から動けば、ちゃんとみんな助けてくれる
──今後のキャリアや成長については、どんなことを考えていますか?
Reona「最近特に考えているのが、自分の役割を明確にすることです。いくらでも仕事はあるので、線引きをしないとパンクしてしまうし、それが会社にとっても迷惑になる。自分にできること、すべきことを意識して仕事するようになったのは、大きな成長だと思います。
こういうとマネジメントも含めて要求値が高そうに聞こえるかもしれませんが、休みはちゃんと取れてますし(笑)、最近はリリースのタイミングも落ち着いてきてます。オンオフの切り替えはまだ苦手なんですが、意識して休むようにしていて。最近はヒューマンビートボックスにハマってます。YouTubeでたまたま見て、いろんな音が出せるってすごいなと思って。」
──Flagshipに合いそうな人は、どんなタイプだと思いますか?
Reona「チャレンジ精神があって、自ら動ける人です。リモート中心なので、受け身だと結構きついと思います。でも、自分から動けば、ちゃんとみんな助けてくれる環境です。私自身も、最初にオフィスに行ったときにすごく温かく迎えてもらって、それが 今もずっと印象に残っています。」
──これからFlagshipに興味を持った方に向けて、メッセージをお願いできますか?
Reona「一番大事なのはECを理解することだと思います。技術やコミュニケーション能力ももちろん必要ですが、クライアントが何に困っていて、どんな施策が必要なのかを理解していないと始まらない。特にFlagshipはECの解像度が高い会社なので、そこをキャッチアップする姿勢は絶対に求められます。
アーキテクトとしては、特に物流、基幹システム、在庫連携、アプリの機能、商品ページの構成、カートで表示する情報など、ユーザーとして当たり前に見ていることを”なぜこうなっているのか?”と、技術的・業務的な視点で見る力が必要ですね。ShopifyやECに関わるシステムは全部つながっているので、そこを俯瞰できると入社後のギャップも少ないと思います。
生成AI革命によりIT業界の変化が加速し、技術主導でビジネスや社会が変革される時代を迎えています。このような環境において、新しい技術の可能性を現実的な価値に変換する『翻訳者』としてのアーキテクトは、極めて重要な存在となっていると考えています。私としては、『この技術で何が実現できるか、どのように活用すべきか』を的確に見極め、具体的な課題解決に結びつける能力を向上させていきたいと考えています。AIが社会構造を根本的に変革する時代において、技術を深く理解し、それを基盤として現実の課題を解決できる専門人材の存在は、社会にとって不可欠だと思います」
インタビュアー:Sho
アーキテクト(システムエンジニア)の募集要項はこちら