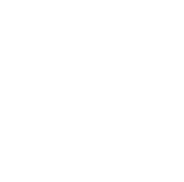ダイバーシティの意義を考えてみる
フラッグシップCEOの神馬です。
私たちフラッグシップは、東京に拠点を置きながら、10ヵ国以上のメンバーが集まる組織です。それぞれが異なる言語、文化、価値観、専門性を持ち、日々新たな価値を生み出しています。
...メンバーの出身国の多様さ故、(安直に)そう言うものの、「ダイバーシティ」って会社で一体何の役に立っているの??という疑問に答えようとするのがこのコラムの目的です。
ダイバーシティの意義を考えるとき、しばしば「円」の比喩が使われます。ある個人の持つスキルや視点を円で表すとすれば、似たバックグラウンドを持つ人々が集まるほど、それらの円は重なり合い、安定感が増します。しかし、異なる視点を持つ人々が集まると、円の重なりは少なくなり、結果として組織全体のカバー範囲が広がるのです。これは、ミシガン大学のスコット・E・ペイジ教授が提唱した「多様な集団は、均質な集団よりも優れた問題解決能力を持つ」という理論にも通じるものです。

フラッグシップにおいても、ダイバーシティは単なる理念ではなく、組織の競争力そのものです。多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まることで、異なる視点がぶつかり合い、思考の幅が広がり、イノベーションの源泉となっています。
引き続き、ダイバーシティの意義や注意すべき観点などについて、説明していきたいと思います。
ダイバーシティの欠如(=同質性の高さ)がもたらす安定性とリスク
組織を急成長させる際、誰かと同じ前職(A社としましょう)からの大量流入や、似たバックグラウンドを持つ人材を積極的に採用することは、即戦力としての期待値が安定し、短期的には有効な戦略です。同じ業界や企業文化を経験してきたメンバーが多いほど、仕事の進め方や価値観のすり合わせがスムーズに進むからです。
しかし、その一方で、カルチャーが特定の方向に寄りすぎるリスクも生じます。同質なグループが形成されることで、意識せずともマイノリティ/マジョリティの構造が生まれ、多様な意見が表に出にくくなる可能性があります。また、固定化された思考が新しい視点を阻害し、組織としての適応力やイノベーションの機会を失うリスクにもつながります。
全ての違いが素直に良いと言ういうわけではない
とはいえ、ダイバーシティが闇雲にあれば良いというわけでもありません。多様な個性が集まる中でも、組織として一貫して持ちたい共通項は必要です。それがなければ、単にバラバラな人の集まりになってしまい、組織としての一体感やシナジーが生まれにくくなります。
フラッグシップでは、多様なバックグラウンドを持つメンバーが協力し合いながらも、共通のパーパス(Develop Maps)とバリュー(Start with Hacker Spirit, Be Professional, Pay It Forward)を大切にしています。「お互いの違いを尊重しながらも、同じゴールを目指す」という意識があるからこそ、多様性が力となるのです。
わかりやすいダイバーシティと、意味のあるダイバーシティ
また、ダイバーシティは、国籍や性別、キャリアの違いだけを指すものではないということにも注意が必要です。本質的には、思考のスタイルや問題解決のアプローチ、価値観の違いこそが、組織の多様性を形作ります。見た目に分かりやすい違いだけに注目するのではなく、より深いレイヤーでのダイバーシティを意識することが重要です。
ダイバーシティの課題とマネジメント
日本国内の企業や団体の多くが日本人、また上層部がほぼ中年男性な一つの理由として、特に暗黙の前提を共有できない相手の存在をめんどくさがる、回避したがる志向があり、それにはその人たちの原体験としてはそれなりの理由があることは理解に難くありません。
多様性が組織にとって大きな価値を生み得る一方で、異なる価値観やバックグラウンドを持つメンバーが集まることで、意思決定が難しくなったり、コミュニケーションのすれ違いが生じたりするリスクもあります。ダイバーシティを活かすには、単に多様な人を集めるだけではなく、その違いを適切にマネジメントすることが必要です。
例えば、意見の対立が生じたとき、組織として「どのように意思決定をするのか」「どのように意見の違いを調整するのか」のルールが明確でなければ、衝突が生産性の低下につながってしまう可能性があります。ルールではなく、リーダーシップで解決する方法もあるかもしれません。また、多様な文化や価値観を持つメンバーが互いに理解し合う機会を意識的に作らなければ、チームの一体感が損なわれ、むしろ分断を生むことにもなりかねません。
フラッグシップでは、ダイバーシティを強みに変えるため、以下のようなマネジメントの工夫を行っています。
• 共通の意思決定基準の明確化
多様な価値観を持つメンバーがいるからこそ、組織として何を重視するのか、どのように意思決定をするのかを明確にすることが重要です。フラッグシップでは、組織のパーパスやバリューを明確にし、それを意思決定の指針とすることで、芯はバラバラにならずに多様性を活かせる環境を整えています。
• 意見の違いを歓迎する文化の醸成
意見の対立が発生したとき、それを「問題」としてではなく、「新たな価値を生む機会」と捉えるカルチャーを大切にしています。多様な意見が表に出やすい環境を整えることで、違いを活かした意思決定が可能になります。
また、人間、案外逆説的に学ぶことも多いものです。反面教師ではないですが、自分とは違う相手の行動や意見を通じて、自分を知り、自分一人では上がれなかった認識の階段を上がることができたりもします。しかも、情報の質や量のギャップがある社外の相手であれば、大きい違いも冷静に判断しやすいものの、前提がそこまでずれていないはずの同僚でさえこんなに違うのかということのショックは、良い意味でも大きいはずです。
• オープンな議論の場の設計
チーム内のコミュニケーションを促進し、互いの考え方を理解し合うための仕組みを設けています(コーポレートコミュニケーショングループが推進しています)。定期的な情報共有ミーティングやチーム横断の交流セッションを通じて、異なる視点が自然に交わる環境を作ることを意識しています。
ダイバーシティの価値を最大限に引き出すには、単に「違いを受け入れる」だけではなく、それを活かすためのマネジメントが不可欠です。フラッグシップでは、異なる意見が自然と交わり、より良い意思決定につながる環境をつくることで、ダイバーシティの真価を発揮させています。
フラッグシップの強みとしてのダイバーシティ
私たちがダイバーシティを重視するのは、それが単なる理念だからではありません。それこそが競争優位性そのものだからです。異なる視点があるからこそ、私たちはより広い視野で課題に向き合い、柔軟で革新的なソリューションを生み出すことができます。
ただこれも、現状のあり方の結果を言語化してみただけで、大元を辿れば何の目的もなくダイバーシティのある組織になっていることや、メンバーの多くがマイノリティ経験をしてきていることから、ネイティブにダイバースな組織であると言えると考えています。
そんなことにも言及しつつ、この先も、フラッグシップはダイバーシティを戦略の中心に据え、さらに強い組織へと進化していきます。違いを力に変え、まだない地図を描いていく。
それが、私たちの進み方であり、誇りです。
2025.02.21
この記事は、パートナー企業の方とのランチの機会をいただいた際、彼にダイバーシティの円の話をしていただいたことをきっかけに執筆しました。インスピレーションをありがとうございました!